受講の受け付けを終了しました
株式会社不動テトラ様は自動設計ツールのDynamoを使うことで、BIM/CIM、ICT活用、点群データ活用など、土木施工業務のさまざまなシーンで効率化を図ることにチャレンジされています。これらの事例をまとめてご紹介していただきます。加えて、大塚商会よりDynamoのサポートサービスについてもご紹介します。
AIと共に進化する建設DX 構想から実践へ
「AIと共に進化する建設DX 構想から実践へ」をテーマにしたオンラインイベントです。全23コースにわたり、最新のAIおよびデジタルツールを事例を交えてご紹介します。本イベントは、建設業界のデジタルトランスフォーメーションを推進し、業務効率化と革新を目指す企業に向けて構成されています。業界の最新動向を把握し、未来の建設業の姿を共に考える貴重な機会をご提供します。

AI・データ活用エンジニアリングAI・IoT・RPACAD(設計支援ツール)営業・業務プロセス効率化業務データの活用オンライン
開催終了いたしました。
最新のイベント・セミナー情報については、イベント・セミナー一覧ページよりご覧ください。
10:00〜10:30
【A01】
基調講演
株式会社不動テトラ様は自動設計ツールのDynamoを使うことで、BIM/CIM、ICT活用、点群データ活用など、土木施工業務のさまざまなシーンで効率化を図ることにチャレンジされています。これらの事例をまとめてご紹介していただきます。加えて、大塚商会よりDynamoのサポートサービスについてもご紹介します。

株式会社不動テトラ
小林 純 氏

株式会社大塚商会 CADソリューション戦略2課
石崎 昇
10:45〜11:15
【A02】
基調講演
日本の大手から中堅の設計事務所ではRevit導入が進む一方、プレゼン・基本計画フェーズはVectorworksを活用している場合も多く、両者のワークフロー断絶が課題にもなっています。そのため、両者の効率的で効果的な連携に期待を寄せる建築設計事務所・内装/店舗設計会社・ゼネコンBIM部門・教育機関の方々を対象に、Vectorworks+Revitという長所を生かし、短所を補い合う設計環境での最新運用手法や技術支援を共有し、より効果の高い設計プロセスや二度手間をなくす効率的な設計手法の有効性を解説します。
株式会社フローワークス 代表取締役
横関 浩 氏
11:30〜12:00
【A03】
生成AIが日々の業務にどのように関わるのか、気になっていませんか? 本セミナーでは、Microsoftが提供する「Microsoft 365 Copilot」を通じて、Copilotの基本機能から、実際に活用されている生成AIの機能までを、デモを交えて分かりやすくご紹介します。さらに、大塚商会ならではの導入支援やサポート体制についても詳しくご案内します。AIとの新しい関係性を、この機会にぜひご検討ください。
株式会社大塚商会 マイクロソフトグループ
稲垣 竜弥
13:00〜13:30
【A04】
従来の建設DXは、特定の業務をデジタル化する「点」の改善にとどまり、情報はデジタル化されてもその多くが活用されずに散逸しているのが現状です。これではAIが真の力を発揮するために必要な「生きたデータ」が十分に集まらず、その恩恵を享受しづらいという課題に直面します。本セミナーでは、建設業務における唯一の統合プラットフォームともいえるAutodesk Construction Cloud(ACC)が建設業のAI活用に不可欠である理由を解説します。ACCは、日々の業務を効率化しながら、その過程で質と量が伴う「生きたデータ」を蓄積し、AIによる未来のリスク予測、品質管理の自動化、コスト効率の最大化といった「予測型建設DX」を実現する基盤となります。
オートデスク株式会社 コンストラクション・ソリューション推進本部 Technical Solution Executive
佐藤 純平 氏
13:45〜14:15
【A05】
2025年4月から、大規模リフォーム工事にも建築確認申請が必要となりました。新築着工棟数が減少する今、注目されているのがリフォーム市場。そんな中、競争力を高める鍵となるのが「ZERO」のリフォーム対応機能です。ZEROでは、リフォームに最適なプレゼン提案や確認申請にも対応する省エネ計算、オート積算と見積書作成といった一連の業務をスムーズに支援。営業・設計・積算の全工程をトータルで効率化し、あなたのリフォームビジネスを強力にサポートします!
福井コンピュータアーキテクト株式会社 営業企画課 主任
田中 信一 氏
14:30〜15:00
【A06】
今後の少子高齢化に加え建設費や住宅ローン金利上昇で新築市場がシュリンクしていく住宅業界。厳しい時代を乗り切るためのDX推進策のツールとしてERPシステムである「住宅マネージャー」をご提案します。データ分析による正確で迅速な経営判断、人手不足に対する働き方改革・新築以外の新たなビジネスモデルへの対応・内部統制強化など大手ビルダー様の事例を交えながらご紹介します。
株式会社KSK ITソリューション事業本部 ビジネスソリューション事業部 営業グループ 部長
山口 靖 氏
15:15〜15:45
【A07】
2024年問題に伴う労働力不足やカーボンニュートラルへの対応など、企業が直面する課題はますます複雑化しています。こうした課題を解決するためには、データ活用やAI技術の導入が不可欠です。HEROZは、独自に開発した将棋AIで世界1位を獲得した実績を持ち、その技術を基にしたAI実装力に強みがあります。本セミナーでは、建設会社やプラント会社でのHEROZ AIエージェント導入事例をもとに、日常的な事務業務や設計業務の効率化・高度化を実現するアプローチをご紹介します。データの実践的な活用方法とともに、AIがどのように未来を形作るのか、その可能性をぜひご一緒に想像してみてください。
HEROZ株式会社 様
16:00〜16:30
【A08】
省エネ適合義務化に対応した省エネ計算ソフトをご紹介します。省エネ計算ソフトを設計者自身が使うことによるメリットや、ソフトの使い方をご覧いただけます。
株式会社建築ピボット 開発部門
田中 里実 氏
10:00〜10:30
【B01】
基調講演
東急建設株式会社は、長期経営計画の戦略実現に向け、人材とデジタルを競争優位の源泉として位置づけ、デジタル活用のための人材育成に注力しています。建設業におけるDXに必要とされる人材育成の実践についてご紹介します。

東急建設株式会社 経営戦略本部 デジタルイノベーション部
小島 文寛 氏
10:45〜11:15
【B02】
基調講演
建築確認申請のデジタル化が進む中、BIM図面審査への対応が注目されています。本セミナーでは、従来の2D図面審査との違いや、BIMモデルから図面を生成するメリット、建築基準法インフォメーションの埋め込み方法など国産BIMソフト「GLOOBE Architect」を活用した実務的な図面作成のポイントを解説します。
福井コンピュータアーキテクト株式会社 カスタマーリレーション部 DX事業推進室
木瀬 憲和 氏
11:30〜12:00
【B03】
生成AIの登場により建設業界でもAI活用が始まっています。今起こっている市場の動きと将来的なAIによるインパクトをご案内します。あわせて、今すぐ始められる生成AIとしてChatGPTとRAGを活用し建設業の業務改革を加速する内容をご紹介します。
株式会社大塚商会 MMオペレーション部 AI・データ活用推進課
大塚 啓太
13:00〜13:30
【B04】
MIIDEL(ミーデル)はAIを活用して画像、図面、書類の比較作業を行うシステムです。変更点を色分け表示することで、目視による見落としを減らし、短時間で大量の図面や画像を比較できます。多様なファイル形式に対応しており、簡単な操作で誰でも使用可能です。目視作業をシステムで自動化・効率化し、働き方改革やDX化を推進することで、従来1日かかっていた作業時間を10分に短縮することも可能です。
株式会社TRIART
本田 康信 氏
13:45〜14:15
【B05】
建設現場の生産性向上と品質確保がますます求められる今、BIMは施工段階でも大きな力を発揮しています。本セミナーでは、施工BIMの基本的な考え方から、実際の現場での活用を分かりやすくご紹介します。コンクリート数量の算出、重機配置計画、掘削モデルの作成など、現場での課題を「GLOOBE Construction」でどう解決できるのかを解説します。
福井コンピュータアーキテクト株式会社 カスタマーリレーション部 DX事業推進室
木瀬 憲和 氏
14:30〜15:00
【B06】
2025年4月に施行された改正建築基準法に対応するため、改正内容に基づいた壁量計算と、許容応力度計算などについての設計支援ツールの使い方を紹介します。
株式会社構造システム 営業本部
藤野 いよ 氏
15:15〜15:45
【B07】
日報やチェックシートなどの現場帳票を電子化するツール「i-Reporter」について、建設業で実際に発生するシーンを通して、より実践的な使用方法をご紹介します。さらに、「kintone」や「MotionBoard」といったほかのツールとの連携で活用の幅は大きく広がり、業務の効率化を加速させます。販売実績5年連続No.1(注)の大塚商会が提供する独自のサポート体制についてもご紹介し、安心してご利用いただけるポイントについてもお伝えします。
株式会社大塚商会 CADプロモーション部 建設プロモーション課
吉國 雄哉
16:00〜16:30
【B08】
省エネ適合性判定の義務化やカーボンニュートラル実現に向けたZEBニーズの高まりにより、ますます、省エネ計算の需要が高まっています。本セミナーでは、初心者の方にも分かりやすい省エネ計算のポイントの解説と、BIMデータを活用した効率的な計算手法をご紹介します。BIMクラウドサービス「B-LOOP」と省エネ計算ソフト「A-repo」を活用した、新しい業務フローをぜひご覧ください。
株式会社イズミコンサルティング BIMソリューション事業本部 営業部
柴田 咲良 氏
10:00〜10:30
【C01】
基調講演
建設業界の「属人性」は、図面や仕様書といったドキュメント間の意味の接続が、個人の暗黙知に依存することから生まれます。本セミナーでは、この課題を解決する新たな手法として、承認のよりどころとなるドキュメントを「状態変化の条件」と定義します。次にACC上で、この条件に基づきヒトが下す意思決定を「トリガー」として設定し、その実行ログをデータベースに記録・蓄積します。これにより、ヒトの判断が「意味ある状態変化のログ」としてオブジェクトデータにも接続され、属人性を排した真の「モノ主体のプロセス」が実現します。その具体的な仕組みと事例をご紹介します。
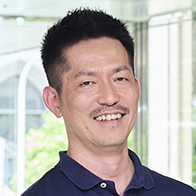
三建設備工業株式会社 DX推進本部 次長
日比 俊介 氏
10:45〜11:15
【C02】
基調講演
地方の人手不足や労働時間問題が大きな課題として2024年・2025年と続いています。一方で、国土交通省より建築GX・DX推進事業の補助金がありますが、具体的な活用イメージが思いつかないというお客様のお声を頂くことがあります。そこで具体的な活用例を列挙し、地場ゼネコンの建設DXに向けた事例紹介、大塚商会の支援例についてご紹介します。
株式会社大塚商会
堀口 広太郎
11:30〜12:00
【C03】
建設業界の効率化を目指した最先端の積算ツール「AI積算」の活用方法をご紹介します。独自開発のAI技術を駆使した積算業務の自動化と精度向上の事例を交え、従来の手作業による積算業務と比較しながら、「AI積算」の導入メリットについて解説します。「AI積算」を利用することで業務のスピードアップやコスト削減、人的ミスの減少が期待できる点に焦点を当て、具体的な導入事例を交えてご紹介します。また、「AI積算」のデモをご覧いただくことで、積算業務の自動化を実感いただける内容です。
株式会社H2Corporation
今関 雄揮 氏
13:00〜13:30
【C04】
急速に進化するAI技術とBIMの融合は、建築設計・意思決定の在り方を根本から変えようとしています。本セミナーでは、GraphisoftのAIの活用、新しいプラットフォームであるProject Aurora、2026年春に開始されるBIM図面審査制度への対応、経営戦略にも資するBIMマネージャーの重要性と認定プログラムのご紹介、そしてGraphisoft製品・サービスの最新動向をご紹介します。建築分野のDX推進と持続可能な組織成長のためのヒントをご提供します。
グラフィソフトジャパン株式会社 カスタマーサクセス、コンサルティングプログラムマネージャー
佐藤 貴彦 氏
13:45〜14:15
【C05】
BIM/CIM設計や点群データ処理において、「データが重すぎて作業が進まない」「共同作業の効率が上がらない」「高額なワークステーションの導入に踏み切れない」などのお悩みはありませんか? 本セミナーでは、これらの課題解決のヒントをご紹介し、建設DXを加速させるための最適なIT基盤をご紹介します。Azure Virtual Desktopを活用したBIM/CIM設計、点群データ処理、そしてAzureによる柔軟な業務環境の構築は、場所を選ばない新しい働き方を実現します。さらに、データ共有や大容量ファイル転送のボトルネックを解消する10Gbps回線の導入メリット、そして処理能力を最大限に引き出す高性能ワークステーションの活用法を徹底解説します。
株式会社大塚商会 CADプロモーション部 CAD戦略推進課
藤田 昌弘
14:30〜15:00
【C06】
気流シミュレーションの設計での活用については浸透してきましたが、FlowDesignerの特徴を把握し活用することで、AIとの連携で効率化を図ることが可能です。本セミナーでは、新たな設計プロセスをご提案します。
株式会社アドバンスドナレッジ研究所 ソリューション技術部 部長
蕪木 智弘 氏
15:15〜15:45
【C07】
建設業の情報管理を革新する「楽々CDM」とクラウドストレージ「Fileforce」の連携で、図面・写真・報告書などのデータをプロジェクト軸で一元管理できます。現場と本社、協力会社との情報共有をスムーズにし、業務効率とセキュリティを両立するソリューションをご紹介します。
ファイルフォース株式会社 様
株式会社大塚商会 CADソリューション戦略2課
碇 修二
受講の受け付けを終了しました
ナビゲーションメニュー