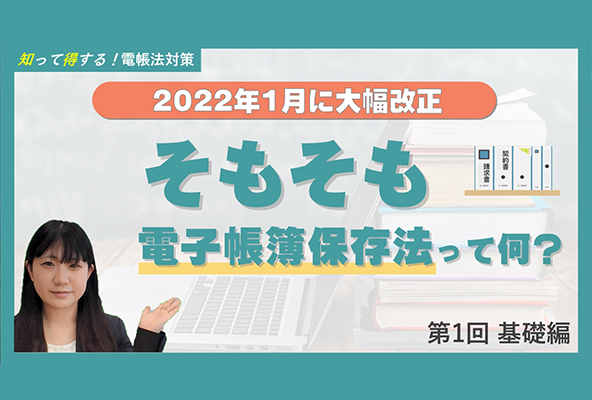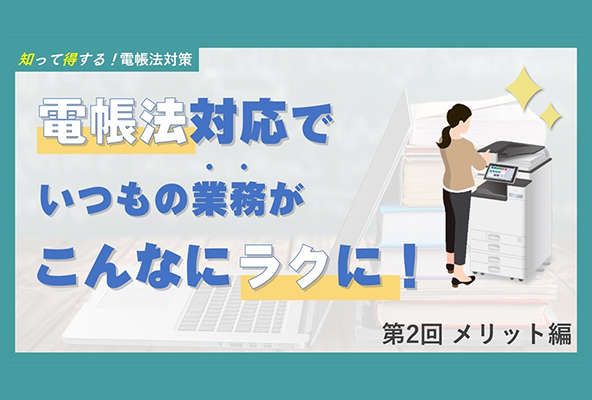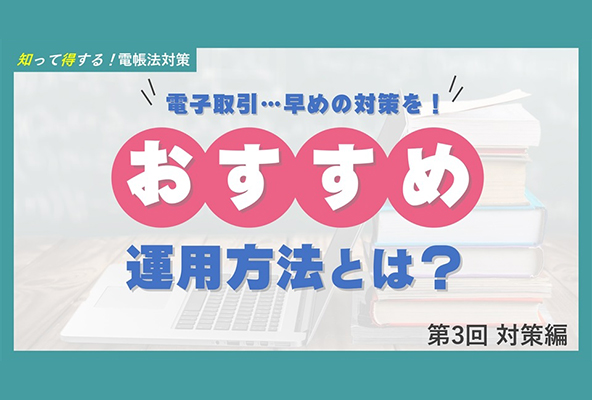大塚商会 インサイドビジネスセンター
0120-210-060(平日 9:00~17:30)
インボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入で何が変わる? 適格請求書の記載に必要なものなどを解説
2023年10月1日から「インボイス制度」が導入され、請求書の保存方式や記載すべき要件なども大きく変更されました。
インボイス制度に対応する請求書を発行できる立場であっても、請求書のフォーマットが間違っていたら、インボイスとして認められないことにもつながるため注意が必要です。では、具体的にどのような点が変更されているのでしょうか。
この記事では、インボイス制度に対応した請求書の書き方や、制度導入による変更点や注意点などを解説します。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは?
インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」です。2019年に消費税増税と共に軽減税率が導入され、消費税に関する会計処理が複雑になりました。これに対応するための仕入税額控除の方式として、2023年10月から運用が開始されました。
インボイス制度の導入により、売り手側は適格請求書発行事業者への登録が求められます。また、買い手側は適格請求書発行事業者の発行した適格請求書(インボイス)を受領し、保存することが仕入税額控除の要件となりました。
なお、インボイス制度の概要は、「インボイス制度の概要とは?」の記事をご参照ください。
適格請求書(インボイス)の書き方
適格請求書としての形式に準拠するためには、以下の項目を記載する必要があります。
- インボイス発行事業者の氏名または名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜きまたは税込み)および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等(端数処理は一つのインボイスにつき、税率ごとに1回ずつ)
- 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

インボイス制度の開始によって変わるポイントとは?
インボイス制度は、現行の制度とどのような違いがあるのでしょうか。ここではインボイス制度の導入により変わる点を三つ紹介します。
請求業務の負担が増す
インボイス(適格請求書)としての要件を満たすためには、現行の請求書の項目に、事業所の登録番号や取引内容の適用税率、税率区分ごとの消費税額を追記しなければなりません。
現在、手書きや古いシステムで対応している場合、経理業務が煩雑化する恐れがあります。人為的なミスやトラブルも増えるかもしれません。
このため、インボイス制度に対応したプロセス、業務フローを再構築しなければならない場合もあるでしょう。ペーパーレス化によって会計処理をシステム化している企業では、インボイスに対応しているのか、もしくは今後対応するアップデートがあるのかをあらかじめチェックすることが重要です。
また、買い手側だけでなく売り手側も、発行したインボイスの写しを7年間保存する義務があります。現行の消費税法では発行者に写しの保存は義務付けられていないため、今後は保存方法についても検討する必要があります。
領収書やレシートも簡易インボイス(適格簡易請求書)として対象となる
インボイス制度では、請求書や納品書のほか、領収書やレシートもインボイスとなります。ただし、領収書やレシートの場合はインボイスの記載要件が一部省略された仕様になっていることから「簡易インボイス(適格簡易請求書)」と呼ばれます。
簡易インボイスの発行を認められる「適格請求書発行事業者」は、小売業や飲食店業、旅行業、タクシー業など「不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う事業者」とされています。
なお、簡易インボイスは、前項掲載の記入例の「6. 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」の記載が不要で、それ以外の五つの要件を満たすと発行が可能です(5. は消費税額等または適用税率のどちらかを記載)。
免税事業者側は仕事が減るリスクがある
適格請求書発行事業者としての登録をする場合、免税事業者のままではできません。また免税事業者との取引では、仕入税額の控除が適用されないため、インボイスを用いた取引をしたい免税事業者は、課税事業者になる必要があります。ただし、課税事業者になると消費税の納税義務が発生するため、収益が現状維持のままでは売上が下がる結果になります。
一方で、免税事業者を継続したとしても、取引先から仕入税額の控除ができないという理由で、取引価格の値引きを求められたり、取引が中止になったりするケースも考えられるでしょう。どちらを選択するかは各免税事業者に委ねられていますが、慎重に検討しましょう。
適格請求書(インボイス)の発行に関する注意点
では、適格請求書を発行するにあたり、どのようなポイントに気を付けるべきなのでしょうか。ここでは適格請求書(インボイス)の発行の注意点を二つ紹介します。
適格請求書の発行にはインボイス制度への登録が必要
適格請求書を発行するためには、課税事業者として、適格請求書発行事業者への登録申請をしなければなりません。免税事業者が2023年10月2日以降にインボイス発行事業者の登録を受ける場合は、登録申請書に登録希望日(提出日から15日以降)を記載すれば、その登録希望日から登録を受けられることになりました。
適格請求書発行事業者の登録申請は、書面の郵送、もしくはe-Taxを利用したオンライン申請の2種類です。
適格請求書(インボイス)の交付義務が免除されるケース
また、適格請求書の交付義務が求められないケースもあります。ただし、このケースに該当するのは以前の方式の免除要件よりも非常に限定的なため、基本的には適格請求書は交付しなければならない前提のもと準備を進めましょう。
適格請求書の交付義務が免除される具体的なケースは以下の5点です。
- 3万円未満の公共交通機関(船舶、バスまたは鉄道)による旅客の運送
- 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売
(出荷者から委託を受けた受託者が卸売の業務として行うものに限る) - 生産者が農業協同組合、漁業協同組合または森林組合等に委託して行う農林水産物の販売
(無条件委託方式かつ共同計算方式により生産者を特定せずに行うものに限る) - 3万円未満の自動販売機および自動サービス機により行われる商品の販売等
- 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)
引用元:国税庁「消費税の仕入税額控除における適格請求書等保存方式に関するQ&A III-2交付義務の免除」より(国税庁のWebページが開きます)
インボイス制度に関するご相談は大塚商会まで
適格請求書発行事業者への登録のために、準備すべきことは複数あります。例えば、適格請求書の要件を満たすための新たなフォーマット作成や、これまでの業務フローやシステム構築を再考するケースなどがあります。とはいえ、これだけ変更点が多い中で、どのように変更や調整を行うべきか悩む担当者の方も多いのではないでしょうか。
大塚商会では、現行の基幹・会計システムにおいても、2023年10月のインボイス制度開始までにシステムのアップデートを順次実施します。大塚商会のソリューションであれば、より効率的に請求書の作成や発行、会計作業が行えます。
SMILE V 2nd Edition 販売
インボイス制度に対応しているほか、売上や売掛から仕入、買掛はもちろん、在庫管理や実績の集計、オリジナル帳票の作成、多角的なデータ分析など幅広い機能がそろっています。過去の履歴データを参照する候補表示などのアシスト機能により、業務効率アップを実現します。また、ExcelやPDFなどのファイル共有もワンクリックで実施可能です。
eValue V 2nd Edition ドキュメント管理
インボイスは電子データとしても取り扱えます。「eValue V 2nd Edition ドキュメント管理」では、紙文書の電子化から、情報改ざんを防ぐためのセキュリティ対策にも対応します。電子帳簿保存法に対応し、タイムスタンプの付与や承認が低コストで実現可能です。
このほかにも、大塚商会では多様なソリューションとノウハウを用いて、企業の皆様の課題解決をサポートします。インボイス制度の対応でお困りの方は、ぜひ大塚商会までご相談ください。

2023年10月から開始予定のインボイス制度。インボイス制度への対応方法を3ステップに分けて簡単に解説した資料を無料でダウンロードいただけます。
資料をダウンロードするには、大塚ID(無料)の登録が必要です。
多数の実績の中から、関連する事例をご紹介
大塚商会から提案したソリューション・製品を導入いただき、業務上の課題を解決されたさまざまな業種のお客様の事例をご紹介します。
運輸・通信業101~1,000名
株式会社仙台中央卸売市場配送センター
製造業101~1,000名
ダイナガ株式会社 セールスマネジメント
電子帳簿保存法への対応が分かる動画を無料で公開中
2022年以降に施行された法改正への対応について、見直しや準備は進んでいますか? 企業がどのような対応を取るべきか改正のポイントを分かりやすく動画でご紹介します。
5分で分かる! 改正電子帳簿保存法とは?
ナビゲーションメニュー