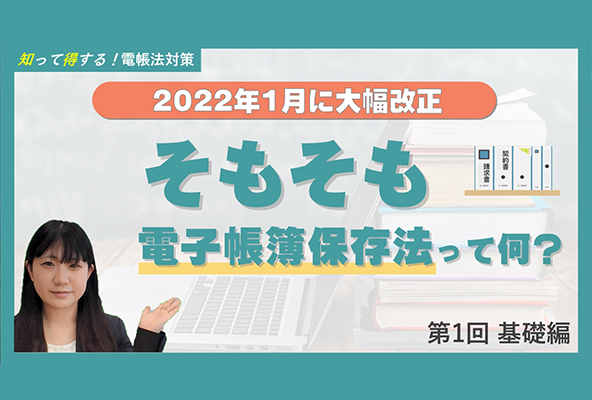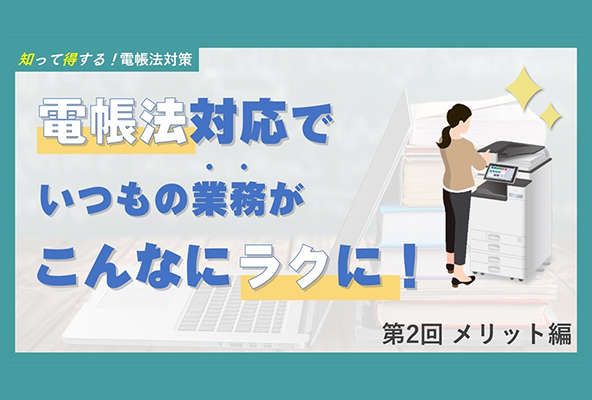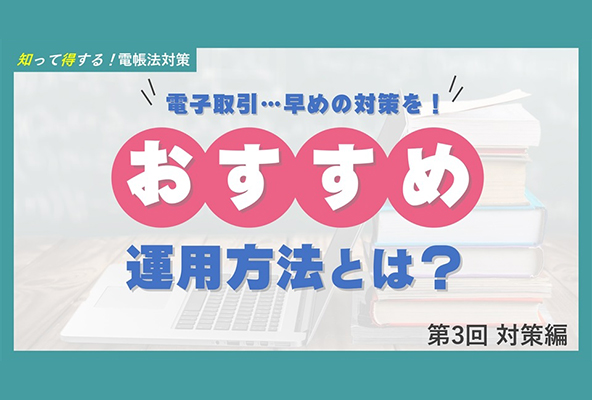規制緩和で領収書の電子データ管理が容易に
電子帳簿保存法は、各税法で紙による保存が義務付けられている領収書などの書類に関して、要件を満たせば電子データによる保存を許可する法律です。また、電子メールなどを介した領収書の保存義務についても規定しています。
この法律では、電子データによる保存方法として「電子帳簿保存」「スキャナ保存」「電子取引」の3種類に区分しています。改正法における各区分の改正点は以下のとおりです。
電子帳簿保存に関する改正事項
- 税務署長による事前承認制度が廃止
- 優良な電子帳簿の場合、過少申告加算税の軽減措置が受けられる
- 最低限の要件を満たす電子帳簿も、電子データによる保存が可能
スキャナ保存に関する改正事項
- 税務署長による事前承認制度が廃止
- タイムスタンプ要件および検索要件が緩和
- 適正事務処理要件が廃止
- スキャナ保存による電子データにおける不正があった場合、重加算税が加重される
電子取引に関する改正事項
- タイムスタンプ要件および検索要件が緩和
- 適正な保存を担保する措置の見直し
改正内容の詳しいポイントについては「電子帳簿保存法改正のポイントと具体的な対応方法」の記事をご参照ください。
電子帳簿保存法改正のポイントと具体的な対応方法
改正前と改正後でこう変わる! 領収書の電子データ管理の方法
ここでは、領収書を含む国税関係書類のスキャナ保存や、電子取引に関するデータ保存の方法について、改正前と改正後を比較しながら解説します。
スキャナ保存の場合
改正によって、領収書を含む国税関係書類のスキャナ保存要件が緩和されました。これにより、領収書の電子データ管理が以前に比べて容易になりました。
紙の領収書をスキャンして保存する場合の要件は、下表の「改正後」の欄をご参照ください。
緩和される「紙のスキャナ保存」要件(2024年時点)
| | 改正前 | 改正後 |
|---|
| 税務署長の事前承認 | 必要 | 不要 |
|---|
| タイムスタンプ | 3営業日以内に付与 | 最長2カ月とおおむね
7営業日以内に付与 |
|---|
スキャナーで読み取る
際の国税関係書類への自著 | 必要 | 不要 |
|---|
電子データの修正時
の対応 | タイムスタンプの付与が必要 | 電子データの変更履歴を
残せるシステムを利用
すればタイムスタンプが不要に |
|---|
| 検索機能 | 取引年月日、勘定科目、
取引金額に加え、日付・
金額の範囲指定検索や
複数項目の組み合わせ検索
ができるようにする | 取引年月日、取引金額、
取引先のみに |
|---|
| 廃棄 | 定期的に検査を実施して
からスキャンした紙を処分 | 定期的検査不要で、スキャ
ンした紙は即座に処分可能 |
|---|
電子取引によるデータ保存の場合
電子取引とは、電子メール、EDI取引、クレジットカードなどによる取引を指します。
2022年1月施行の改正では、電子取引でやり取りする領収書などについて、紙に出力して保存することは認められなくなり、電子データ保存が義務化されました。
タイムスタンプの付与期限や検索機能の緩和については、スキャン保存の場合と同様です。
なお、基準期間の売上高が5,000万円以下の小規模事業者が税務調査などにあたってダウンロードデータを提供できる場合は、全ての検索要件が不要になります。
各電子取引の領収書の保存方法は以下のとおりです。
電子メールによる領収書
電子メールによる領収書を授受する取引も電子取引に該当するため、電子データ保存が必要です。
電子メールそのものを、また添付ファイルにより領収書を授受した場合はその添付ファイルを、ハードディスクやコンパクトディスク、DVD、磁気テープ、クラウドなどに記録・保存します。
ただし、電子メールおよび添付ファイルは、受領者によって修正変更ができてしまうことがあります。そのため、受領したデータにタイムスタンプの付与がない場合は、受領者がタイムスタンプを付与する、または事務処理規定にもとづく適切なデータ管理を行わなければなりません。
Webサイトやクラウドサービスからダウンロードする領収書や、サイト上に表示される領収書
電子メールによる領収書と同様に必要に応じて受領者がタイムスタンプを付与、または事務処理規定にもとづく適切なデータ管理を行います。
また、PDFやスクリーンショットによる領収書のデータを検索できる形にして保存します。
クレジットカードや交通系IC、スマートフォンアプリなどによる電子決済
日付や取引先、金額などのデータを、修正の記録が残るシステムまたは修正できないシステムで利用していれば、電子取引における要件を満たしていることになります。
一方、クラウド上に一時保存したデータをダウンロードして保存するシステムの場合は、電子メールやダウンロードしたデータと同様の方法で保存する必要があります。
EDIシステム
電子決済と同様に、領収書に一般的に記載されるデータを修正の記録が残るシステムまたは修正できないシステムを利用していれば問題ありません。
一方、クラウド上に一時保存したデータをダウンロードして保存するシステムの場合は、電子メールやダウンロードしたデータと同様の方法で保存する必要があります。
電子帳簿保存法一問一答(Q&A)(国税庁のWebページが開きます)
原本の保存方法や保存期間
改正に伴い、定期的な検査および再発防止策である適正事務処理要件が廃止されました。これにより、スキャナ保存後の紙の領収書などの保存が不要になります。
改正前は読み取り後、領収書の原本とスキャナ保存した内容が一致しているかの確認のために原本書類の保管が義務付けられていました。保存期間はその事業年度における確定申告書の提出期限の翌日から7年間(欠損金の繰越控除を受ける場合は最長10年間)と長期間でした。
改正後は、定期検査不要でスキャンした原本はすぐに処分できるようになっています。
改正電子帳簿保存法で電子データに切り替えるメリット
電子帳簿保存法の改正を機会として電子データに切り替えることでさまざまなメリットが得られます。
具体的には、以下のとおりです。
テレワークにおける利便性が向上し、テレワークの浸透につながる
特に経理部門では書類の作成や管理など紙を扱う仕事が多いことから、テレワークが難しい傾向にありました。しかし、領収書をはじめとするさまざまな書類を電子化すれば社外でも仕事ができるようになり、テレワークの浸透につながるでしょう。
ペーパーレス化によるコスト削減が実現する
電子データとして領収書などの書類を保存できれば、紙自体のコストや印刷費、保管費用、郵送代、倉庫への運搬費用など各種経費を削減できます。トータルで大きな費用削減効果が得られるでしょう。
検索性の向上によって業務効率化を図れる
従来は、取引先からの問い合わせや調べものを行う際、必要な情報を手作業で膨大な書類の中から探さなければなりませんでした。電子保存であれば、検索機能を使ってすぐに必要な情報を探し出せるため、業務効率アップを図れます。
セキュリティを強化できる
紙で保存した場合、盗難や紛失などのリスクがありました。電子保存の際にアクセス権限などの適切なセキュリティ対策を講じれば、高いセキュリティ環境の下で管理できます。
保存管理のための負担を軽減できる
前述のとおり、改正前は領収書などの原本を一定期間保管しておかなければなりませんでしたが、改正後は定期検査不要でスキャンした原本をすぐに処分できるため、保全管理の負担が軽減されます。
領収書の電子化は大塚商会におまかせください
領収書などの帳簿書類の電子化をご検討の方は、ぜひ大塚商会におまかせください。
大塚商会では、電子帳簿保存法における四つのプロセスに対応したソリューション・製品をご用意しています。導入時から導入後までワンストップでサポートを提供します。
プロセス(1)書類を電子化する:スキャナ機能
近年の複合機は、スキャナ機能がついているものがほとんどです。スキャナ機能を利用すれば、書類の電子化も簡単に行えます。大塚商会では、エントリーモデルから、高性能のモデルまで、幅広いラインアップをご用意しています。
複合機製品を詳しく見る
プロセス(2)電子化時点で書類が存在していたことを証明する:タイムスタンプ
paperlogic電子書庫(ペーパーロジック)
契約書をはじめとした法定保存文書を全て電子化し、スキャナ保存文書と電子取引データを総合的に管理できるソリューションです。電子帳簿保存法に対応しています。
安価なサービスですが、タイムスタンプは押し放題で、一括検証も行えます。
paperlogic電子書庫(ペーパーロジック)
プロセス(3)電子化した書類を管理する:文書管理システム、会計システム
文書管理システム「eValue V 2nd Edition ドキュメント管理」
「強力な検索機能」「万全のセキュリティ」「電子帳簿保存法への対応」、これら三つの特長を持った文書管理システムです。エクスプローラー感覚でドキュメントを階層管理できるほか、ファイルの新版・旧版を識別して版管理のトラブルを防止します。
また、ドキュメントの発行日・失効日を指定することで、抜け防止にも有効な有効期限管理が可能です。さらに、フォルダーやドキュメントに対し、ユーザーやグループ単位でアクセス権限を設定できることから、強固な情報漏えい対策を講じられます。
文書管理システム「eValue V 2nd Edition ドキュメント管理」
プロセス(4)証憑(しょうひょう)を処分する:文書の溶解処理ソリューション
安い・簡単・安心な機密文書の溶解処理サービス「Webメルティ」
低コストで機密書類を処分できる溶解処理サービスです。
シュレッダー処理とは異なり、溶解処理を行うため文書が復元される可能性がゼロです。バインダーにとじられたファイルもそのまま処理が可能なので、いちいち書類を外す作業も必要もありません。段ボールで回収し、無開梱(かいこん)のまま溶解処理を行うことができます。
Webメルティ(たのめーる)
領収書をはじめとする文書管理サービス導入のご相談は大塚商会まで
ここまで、改正電子帳簿保存法に対応する領収書の扱いをご紹介しました。
電子帳簿保存法が改正されたことで要件が緩和され。領収書などの取引関係書類の電子化を導入しやすくなりました。なお、電子取引ごとに領収書の保存方法が異なるため、注意が必要です。国税庁が発表している「電子帳簿保存法一問一答」をいま一度確認しておきましょう。
領収書をはじめとする文書管理サービスの導入をお考えのご担当者様は、多様なご要望に合わせた豊富な文書電子化、管理サービスの導入に際し豊富な経験と実績のある大塚商会へお問い合わせください。
多数の実績の中から、関連する事例をご紹介
大塚商会から提案したソリューション・製品を導入いただき、業務上の課題を解決されたさまざまな業種のお客様の事例をご紹介します。
電子帳簿保存法への対応が分かる動画を無料で公開中
2022年以降に施行された法改正への対応について、見直しや準備は進んでいますか? 企業がどのような対応を取るべきか改正のポイントを分かりやすく動画でご紹介します。